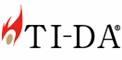ツイッターのまとめだけではなく、漫画家の集まりでも「あの発言はけしからん」論調を耳にします。
まあ、生まれているのは生まれているけど、たいして育っていないのではと思うのが正直なところですし、生まれない作品もあるなとも思います。
「ウルトラマンは?」「マブヤーは?」ということを言われてしまいそうですけど、そういう細かい話ししてても仕方ないと思うわけですよ。
漫画を書いてたりそういう路線を目指す人は「沖縄の作品はー!!ムキー!!」って怒ってる暇があれば、なぜそうなってるのか考えて作品に活かす、さっさと手を動かすほうがよほど建設的かつ前向きな発想だと思うんですね。
郷土愛や作品への愛情も理解できますが、愛情だけで上手くいくわけでもないですし、そこはサラっと。
私が漫画描きをするうえでは、友人から色んな意見を聞きます。この手の話を語るほど漫画を読んでいないもので・・・そこで友人の話を参考に話をしていくのですが、9割方冷静な意見というよりも「好み」を語っているとか、好みの話しになっていくわけです。
どの作品にせよキャラクターにせよ、個人個人の好き嫌いがあるわけで、お互い好きな作品自慢をしてても分析に役立つ議論はできませんから、極力そういうのは極力抜きにして要因を分析していきます。
まあ最終的には好みの作品傾向を応援したくなるのは仕方ないことですが。
たとえばウルトラマンを例にすると、私も再放送で見たウルトラマンセブンや、レンタルで見たウルトラマンタロウは大好きでした。あまり話は覚えてませんがウルトラマンも怪獣も、警備隊の乗り物もむちゃくちゃかっこよかった。
これをウルトラマンガチ勢の方はちゃんとした名称を使いながら語っていくわけですが、昔見ててかっこよかったという印象と好感しか持っていない人に、ガチ勢がガチの話すると正直ウザったくなってしまいます。
私がサバゲーのラジオ番組を企画するときに注意しているところでもあり、初心者にもわかりやすく、一方でガチの人の枠も作るという住み分けをする必要もあります。同じ趣味でも考え方が違うもんです。
本題に戻ると”ウルトラマンが沖縄生まれのコンテンツ”かというと、脚本家に金城哲夫さんという南風原町出身の方がいたという話であって、皆さんご存知のとおり製作は円谷プロダクションです。チブル星人もキングジョーも誇りに思うのですが、「沖縄生まれ」というのはちょっと無理やり感じがあるかなと思うのですが・・・。
金城さんは亡くなられてますが、報道等で金城/ウルトラマン特集を組まれると反戦平和にくっつけたがる流れにも違和感がありますね。後ほど詳しく書きますが、沖縄でオタクコンテンツが生まれにくい最大の要因がコレだと思ってます。
琉神マブヤー流行りましたね。
オタクコンテンツというには幅広すぎる人気でした。
うちの家族も大好きでした。大好きでしたというのは過去形だからです。
クーバーとか大好きだったんですけどね。
琉神マブヤーは悪者のマジムンを殺さないことと、マジムンにも言い分があり、キャラクター性もあってすごい人気が出ました。
ただ、ある作品を出したとたん、子供も大人もマブヤーの話しが減った感じがするんです。
うちの子供もまわりの子供も、マブヤーの真似しなくなったんですよ。
ガキンチョが突っかかってくるときは、だいたい「スーパーメーゴーサー」でしたからね。
子供達がそれ言わなくなったんです。
子供達がマブヤーの話をしなくなった時期の作品というのが、復帰前後の話。
大人の事情を盛り込んじゃったわけです・・・。
大人の事情といっても、大人が見ても意味不で違和感のある事情ですね。もちろんそれが心地いい人がいるとは思いますし、そういうの心地いいって思った人が盛り込んだんでしょうけど。
オタクコンテンツが生まれない事情として「沖縄特有の大人の事情」があるのではないかと思ってます。
マブヤーは最初の頃のほんわかした空気では大人気だったのに、アメリカーがみたいな大人の事情を入れたために、子供達も大人もひいたんじゃないかなと。
ちょうど映画化された直後だったと記憶してますが、映画化まではかなりよかったし、沖縄では最も成功したコンテンツだったと思います。
今マブヤーの話をするちびっ子って、リアルタイムで見てなかった世代の小さい子供達です。
大人の事情というのは、何と言いますかぶっちゃけ言うと反戦平和とか基地反対的な主張を入れておけば合格、それ以外は不合格というものです。
沖縄では大事なことであり問題なのかもしれないですけど、もうそろそろ何か新しいアプローチがないとダメじゃね?って率直に思います。
沖縄が一時的に舞台になったり登場する作品にはRBCで放送されていた「blood+」がありました。
この作品はちょっと見てたのですが、沖縄から始まって最終回も沖縄で終っていました。
宮城(みやぐすく)や謝花というキャラクターが出てきたり、中央パークアベニューとか山原が出てきたりして沖縄バリバリに登場してました。
ウルトラマンと同じように「沖縄を舞台にしてるぞっ」てもっと盛り上げればいいのにと思うのですけどね。
バトルものの作品であり、反戦平和が入ってないから、沖縄のコンテンツと名乗るには不合格って流れなのかもしれません。もしかすると。
私が漫画を描こうと思い、投稿しようと思い立った時、先にやったことはマーケットリサーチです。
それと沖縄の漫画の情勢を調べて、自分の作品に取り入れるところから話の構成をはじめました。
漫画作品の2割くらいは沖縄戦を扱った作品みたいです。
画像で「沖縄漫画」とググると3割くらい沖縄戦関係の作品が登場します。
沖縄戦を語り継ぐことも大事なことです。
ですが漫画でオチとか作風が読まずして予測できます。
・戦争の足音が聞こえてくる
・米軍上陸、住民が巻き込まれる
・戦況悪化・何とか生きながらえるも友人や家族が死ぬ
・終戦、二度とこんな悲劇を繰り返してはならない
・アメリカーがー、日本兵がー ・・・etc
戦争しちゃダメってサバゲーマーかつミリオタの俺だってわかりますよ。
当たり前のことじゃないですか。
そのおかげでサバゲーもミリオタも楽しめてますから。平和には感謝してます。
ただ、大きな話をすると平和ってどうやって維持されているのか。
現実的な捉え方もあるでしょうし、平和平和って唱えれば平和は維持できなっても考えてます。
オタク的に大好きな作品と言えば「機動戦士ガンダム」シリーズがありますが、沖縄の大人の事情を当てはめて考えてみましょう。
・ジオン軍が蜂起し、一年戦争がはじまる
・仲間が命を落としながらも戦いを切り抜ける
・一年戦争終戦
・二度とこのような悲劇を繰り返してはならない
・・・Zガンダムは生まれませんね。ハイ。
まあ、ニュータイプが増えてお互い分かり合える時代がきたとき宇宙世紀のシリーズは終るのではないかと思いますけど。
ガンダムの場合を考えると、連邦にもジオンにも事情があり、魅力のあるモビルスーツや艦艇があり、濃厚なストーリーだったために今も人気で新作が登場しています。かっこよさだけではない人間ストーリーであると解釈してます。なのでファン層が厚く、また、単にガンダムファンといっても色んな人がいます。
「オタクコンテンツ」ってのを何を指しているのかというのがありますが、ウルトラマンとかマブヤーみたいな広い年代をカバーしている作品というよりも、ガンダムなどのようにもっと狭い枠を指しているんじゃないかって感じます。マブヤーがオタクコンテンツなら、応援していた人はみんなオタクです。
ガンダムは昔はガンダム好きというだけでオタク扱いでしたが、今はもっとファン層が広くなっていますが、はやりオタク寄りかなという印象派あります。
オタクにも色々あって、アニメが好きな人もいればゲームが好きな人もいます。我々みたいなミリオタと呼ばれる軍事に興味を持つオタクもいます。軍事でも様々で艦艇や航空機、銃器だったり様々ですし、航空機でも軍用機に限らず民間機に至るまで趣味としている航空機オタクもいます。
沖縄でも映画上映された作品に「ガールズ&パンツァー」がありますが、”ガルパンおじさん”と呼ばれるオタクも登場しています。
私も好きなんでガルパンおじさん一歩手前というところです(笑)
単に好きということだけではなく面白い作品だなと思っているのは、色んな人が引っ張られているところですね。プロレスラーの蝶野正洋さんもガルパンおじさんだそうです。マニアック×女の子で上手くいったパターンです。
戦車で戦っているのに誰も死なないという不思議設定もアニメならではで、マブヤーの「誰も殺さない」という部分に共通します。
今風のスポ根アニメと考えればわかりやすいかもしれません。
一方で戦車マニアのガチ勢からは「あんなのありえない」と言う人もいますが、最終的には好みの問題で、議論しても決着がつくことではないのでここでは除外します。
あと、ガルパンの面白いところは、作品と地域が連携しているところです。
いまや茨城県大洗町がガルパンの聖地となっています。
ガルパンファンの友人で「大洗聖地巡礼」をした人たちが口々に言うのは、町の人もやさしく、料理もリーズナブルで美味しく、また行きたいとのことでした。本当にいい町だそうです。私も余力ができたら行ってみたいです。
「あそびにいくよ」というアニメでは沖縄が舞台になってて、県立図書館や市民会館、エンダー(A&W)がでてきて聖地になってますが、ではこうした施設や店舗がアニメと連携しているかというとそういう話しは聞かないですね。
http://d.hatena.ne.jp/paffue/20141026/1414290613
ガルパンはそのあたり地域ぐるみで力入れて連携してるのもすごいなと思います。
お店ごとに押しキャラがいるらしくて、パネルが展示されて居たりします。
沖縄だって美味しい料理も綺麗な海もあるんですから、同じような連携ってできるはずなんですよね。
いや、たぶんやっているし、やろうと画策してる人が確実にいるはずです。
「沖縄にオタクコンテンツを生む」=「聖地巡礼の地」にしたいということは、クリエイターなら少なからず考えることでしょう。
でも、オタクコンテンツが生まれないと言われてしまう。
もちろん聖地ができれまくればいいかと言えば、一部のマナーが悪い人や空気が読めない熱狂的ファンのおかげでマイナス面もあるでしょう。
しかしこの手のコンテンツでは聖地ができるか否かはちょっとした指標になるのではないかって感じます。
聖地巡礼の地といえば「けいおん」の聖地巡礼に行く友人がいます。
沖縄で漫画やアニメ作品の聖地を作るなら「けいおん」みたいな感じのノリでも良いのでは?という友人もいます。
まあ、やんわりした作品ってのでも良いかもしれないですが、バトルものやガンアクションが登場する作品を作ることに対し「沖縄でこんなの作ろうなんてけしからん!」という風潮が、結果的にオタクコンテンツが生まれない原因になっているのではないかと。だからガルパンを押してるわけです。大洗町の町の人たちとの連携も事例として面白いですし。
空想作品に対してまで反戦平和とか基地問題を押し付けたがる風潮ってのも、いい加減どうにかならないものかと。
私は小さい頃から銃とか戦闘機とか好きで、親からたびたび怒られていましたが、今じゃ親もいっしょにサバゲとか自衛隊関係の仕事してます。昔は今よりも自由度がなくて、人の目もあったので怒らざるをえなかったそうです。
じいちゃんもばあちゃんも基地従業員で、学校でも色々嫌な思いしたみたいで、その延長だったとか。そういうところなんです沖縄って・・・。
大人の事情も沖縄としては伝えないといけないことなんでしょうけど、受け手が作り手の意図どおりに好意的に見てくれるかは?です。
沖縄でコンテンツを作ったところで、受けて側が違和感を持ってしまえばそれで終わりです。
「大事なことだから」とゴリ押しされれば、もういいやって萎える人もいるでしょう・・・表に出さなくても。
あんま政治的な話しに結び付けたくはないのですが、重要なことだし関係あると思うので触れます。
この数年は東シナ海がキナ臭くなってて、平和をどう維持して行くか考える機会も増えていると思います。
沖縄の人はのんびりしてるなと思ってる人もいるでしょう。
いつも基地問題のことで不機嫌な姿勢を見せつつも、補助金はちゃっかりよこせという沖縄的な政治にうんざりしてる人もいるでしょう。
2000年台はじめまでは沖縄ブームでしたが、今じゃ沖縄嫌いの方もたくさんいるんです。残念ながら。
まあ、上記のような報道が続く限り歯止めが利かないかもしれませんが、みんながみんなこんな人ばかりじゃないので念のため・・・
今野流れを見ていると「嫌沖」が来るのは間違いないと思っています。っていうか来ています。間違いなく。
沖縄県民としてはショックなことかもしれません。だからちゃんと冷静に考えないといけない。
変えられることは変える努力をしましょう、変えられないことはそのまま受け入れましょう(by加藤諦三先生)
沖縄なんかどうでもいいんじゃね?っていう流れができれば、ますます沖縄を舞台にしたオタクコンテンツなんて生まれない島になるでしょうね。あってもなくても良い趣味上のコンテンツなわけですし、客層が狭い(その分熱狂的になりうるのですが)業界ですから。
そういう事に気づかない人が「何で何で」と騒ぎ、また、原因を知っているはずの人たちが原因を知らんふりしている。
一連のツイッターの話題では、そんな感じの印象を受けてました。
ツイッターの発信元の方のプロフィールを見たところ、こういう人がオタクコンテンツを誘致したところで、上記に描いたようなワンパターンの沖縄作品になるだろうなというのはなんとなく予測でき・・・もしオタクコンテンツを誘致しようってなっても、なんやかんやで反戦平和、さらには反基地的な流れに誘導されてしまうパターンになりそうな気が。
「沖縄はいいぞ~」「沖縄の心は反戦平和」のゴリ押しだと、飽きられちゃうでしょう。
ってか飽きられてますよたぶん。
もうちょっと自由に作品を生み出せる風土がないと、この先本当に厳しいんじゃないかなと・・・。
こんな環境ですので、せっかく描いた私の漫画も売れなくなりますね(笑)
9月に印刷できる運びとなりそうな状況のなか、私なりのこういう流れで抗い方を書いてみます。
めっちゃ営業です。
元々は私の本業の刺繍のキャラクターたちで、サバイバルゲーム向け商品のキャラクターでした。
これをコミックチャンプルーに持ち込むさい、「印刷化したら釣具屋でも売れる」という理由で釣りの話しに変更しました。
このブログを昔からご覧いただいている方ならわかると思いますが、釣りに関するネタは尽きません。
工夫としてはキャラクターやストーリーにはできるだけ沖縄っぽさを出さないようしてます。
既存の「沖縄ブランドに乗っからない」ためです。
生えてる樹木とか釣れる魚が沖縄ってくらいでいいかなと。あとはご当地妖怪くらいなもんです。
既存の沖縄ブランドに乗っかって売ることは労力的にたやすいです。
ただ、沖縄ブランドが前ほど勢いはないし、書き綴ったとおりマイナス要因も多いと思ってるので、沖縄ブランドに乗っからない。
沖縄のルアー釣りをまとめた本がないので、漫画で書いてしまえば需要があるかもしれないし、これがウケてくれればなお良いなと。
読んだ人は恐らくルアー釣りに興味がある人たちでしょうから、読んで「へぇ~、知らなかった」っとなればOKっていう程度の考えです。
(画力はないので、できる範囲でいいやって感じです・・・地味に練習中ですが)
私が手がけている釣り漫画の魚は亜熱帯/熱帯の魚ですから、沖縄だけではなく奄美でもオーストラリアでもグアムでもフロリダでも応用できるはずです。もちろん安全管理とかマナー啓発のケアは重視してますよ。それ伝えるために描いた”釣りの教科書”ですから。
沖縄ブランドの捉え方は、オタクコンテンツに限らず、観光業や農業、各種サービスに言えることだと思います。
本当に前ほどブランド力があるのか、ブランド力を上げるために我々は何をしていけばいいのか、タブーとかそういうのをとっぱらって見る必要があるんじゃないかなと。
先日、印刷化にむけて書店へ出向き、表紙の方針を決めるための調査を行いましたが、サブカルやオタクコンテンツに限らず、沖縄コーナーって沖縄のイメージとは思えないくらい暗いんですよ。暗い本の中に明るい本が埋もれてる感じで。
マジメな本がある中で漫画を置いてもらうわけですから仕方ないですが、暗い本の中に目立つ表紙を当てるのが吉とでるか凶と出るか。まあ、釣具屋で売ってもらうことをメインにしてますからいいのですが。
沖縄の漫画全て読んでないので断言はできませんが、「どうせ最後に言いたいことは反戦平和とか反基地でしょ?」って思って身構えて読んでしまいます。やっぱりなーと思う時ほど残念な気持ちになることもあります。
そういう印象付けされたら、わざわざ読まないんじゃないですかね。
この手のオチを期待している人意外は・・・オタクの人って概ねそういうの期待してないと思うんですね。
オタクの人ってもっと自由でありながら、実はシビアな人たちだと思うんですよね。
私自身オタクですので。
趣味にはそれなりにお金も使います。
紙袋に何十冊の同人誌を買って行く人でも、何でも手を出すわけじゃなくて結構吟味してると思いますよ。
普通の人なら趣味にかけられるお金には限りがありますから。
思っているよりもシビアなんで、事前情報や最初の印象で動く人も多いはずです。
そういう人たちを誘致できる仕組み、つまりオタクコンテンツが生まれるなら万々歳ではありますが、沖縄産の作品の有り方について、もっと冷静に目を向けないといけない時期じゃないかなと感じました。