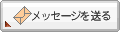2022年01月27日
新刊完成、雑感
遅ればせながら、新刊完成しました。
たぶん今持ちうる技術はすべて使いましたが、月末のおでライが延期になってしまったので、披露は2月以降となりました。
今回はISBN/書籍JANのバーコードなしの同人誌というポジションなのですが、本編が4話分(102ページ)と結構なボリュームあると思います。

さて、雑感というかガス抜き。
たぶん今持ちうる技術はすべて使いましたが、月末のおでライが延期になってしまったので、披露は2月以降となりました。
今回はISBN/書籍JANのバーコードなしの同人誌というポジションなのですが、本編が4話分(102ページ)と結構なボリュームあると思います。

さて、雑感というかガス抜き。
一旦出し切ったあとは真っ白になってしまい何もやりたくない時もあるのですが、何か動いていないとストレスが溜まる性分でもあるので、今まで苦手意識があって使ってこなかったイラレの勉強をしてみたり、思いついている話のネームを3話分書き出してみようとしたりと気持ちを切り替えていきます。
描かない時間というのはなかなか大敵で、休むと感を取り返すまでに少し時間がかかったり。
そんなわけで、ちょっとした時間でも漫画やそれに関連することを描くようにしてるわけです。
漫画家が業界に飛び込むのは何歳からでもできますが、実際はどうしても年齢がつきもので、漫画賞などでは年齢が高くなるほど不利になると言われています。
若い人なら伸びしろを期待できるので、多少の粗があっても有利になりがち、青田買いってやつでしょうかね。
漫画賞は年齢制限はありませんとしていても年齢を書く欄があります。ちょっと前にはいかに嘘をつかずに年齢をごまかすか、という事を真剣に考えました(笑)
書きたくない人もたくさんいる事でしょう。
まあ、完成度の高い原稿を描けばそれで済む話なんですが、それがまた非常に難しい。
何をもって完成度が高いとするか。
限られたページの中で、どこにパラメータの主軸を置くか。実はこれがめちゃくちゃ難しい。
絵一つとっても、キャラなのか画風なのか。線のシャープさなのか数なのか…何を持って画力が高いとするのか。
それとも背景描いときゃいいのか。
雰囲気なのか感情表現なのか、それとも設定なのか物語の構成なのか演出なのか。
演出ってなんだよ意味わからんのだけど(笑)
言いたい事が山ほど……
ページや時間がふんだんにあれば、それぞれを高い次元で両立することはできるでしょうけど、いわゆる「持ち込み」でも、ページ数が多いほど読む編集者の負担増になってしまいます。漫画賞ではページ数の制限があったりしますし、一部を除いては普通は8ページ単位の構成です。
恐ろしく面白いネームが描ければ別なのでしょうけど、長い作品って逆効果の場合がほとんどなんです。
自分が編集者だったとして、他の作業してる時に時間空けさせられて別の原稿読まされるわけですから、それは完結に描かれているほうがいいでしょうね…。
あと、読み手の思考・・・自分が思うに、文系か理系かで、とらえ方が全く違ってくるのではないかと。
最近から漫画を色々読むようにしてますが、雰囲気重視の漫画とか絵が可愛いだけの漫画はあまりそそられず…一方で何らかの知識を得られる作品は図柄に関係なしに好きだったり、設定の狂いとかに目がいきがちな性格です。これは自分自身が理系タイプだからだろうなと。
読み物でも圧倒的に解説書とかが多いですし、文章を書くのも解説を作るのは何の苦でもありません(この記事も解説の一種かも)
感情表現を追求するよりも、仕組み作りが得意な脳みそでできていると自負しています。
そんなわけで新刊が完成し、これを出版社等への営業へ活用しようと考えているわけですが、果たして「仕組み作り」を得意とするオッサンの書いた漫画がどのくらい受け入れられるのか…編集者ってたぶん文系出身の方が多いと思うんですよね。水と油という感じです。
水分であるお酢と油、そこに卵があればマヨネーズの完成なんですが、その卵たる漫画原稿の確保が非常に難しいって感じでしょうか。
業界人の事をクリエイターと言います。
その業界の中で生きていくために流れをとらえ、それを取り入れていくことは必要な事なんだろうなと。
経験談なのだから間違いない事だと思います。
一方、業界にいる事。流れに乗ればクリエイティブと言えるのか?という疑問もあります。
何かを生み出す人のことじゃないのかと。
そんな事考えるから最前線に上がれない、ということになるのですが。
今考えれば、もっと早くから漫画に取り組んでおけばよかったと後悔してます。
中高生の時には一応は描いてたんですよ。見せられるレベルじゃないですけど(笑)
その時続けて今のように取り組んでいれば、たぶん「青田買い」されていたかもしれません。
しかし、もしそうしていたらネタで悩んでいたことでしょう。
その時は釣りにサバゲーに、仕事に明け暮れていた日々があったわけで、今描いている漫画はその時の経験のアウトプットなわけですから。
後悔はしてるけど、後悔してませんみたいな(笑)
ラジオのテレフォン人生相談で、加藤諦三先生が「変えられる事は変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう」とおっしゃっています。
後悔してても変えられないことは変えられないんで、変えられる事をどんどんやっていくしかありません。
そこに自分の「仕組み作り」が役立つわけです。変える事、ですね。
流れに乗るのが一番楽ですが、新たな流れを作る…仕組みを作り変えてしまえばいいじゃない。
決して簡単な事じゃないのだけれど、これこそかなりのクリエイティブじゃないですかね。
「漫画に機能を持たせる」
これが自分が当面目指すべき仕組み作りなんだろうなと。
そういや、釣り方を開拓したり、オモチャって言われてた機材で精度の高い刺繍作る手法編み出したり
その手の事色々やってきたわけですし。
たぶん手法を追求してどっかで諦めなければできるなと。
というわけで、ちょっとした閉塞感の中ちょっとガス抜きさせていただきました。
描かない時間というのはなかなか大敵で、休むと感を取り返すまでに少し時間がかかったり。
そんなわけで、ちょっとした時間でも漫画やそれに関連することを描くようにしてるわけです。
漫画家が業界に飛び込むのは何歳からでもできますが、実際はどうしても年齢がつきもので、漫画賞などでは年齢が高くなるほど不利になると言われています。
若い人なら伸びしろを期待できるので、多少の粗があっても有利になりがち、青田買いってやつでしょうかね。
漫画賞は年齢制限はありませんとしていても年齢を書く欄があります。ちょっと前にはいかに嘘をつかずに年齢をごまかすか、という事を真剣に考えました(笑)
書きたくない人もたくさんいる事でしょう。
まあ、完成度の高い原稿を描けばそれで済む話なんですが、それがまた非常に難しい。
何をもって完成度が高いとするか。
限られたページの中で、どこにパラメータの主軸を置くか。実はこれがめちゃくちゃ難しい。
絵一つとっても、キャラなのか画風なのか。線のシャープさなのか数なのか…何を持って画力が高いとするのか。
それとも背景描いときゃいいのか。
雰囲気なのか感情表現なのか、それとも設定なのか物語の構成なのか演出なのか。
演出ってなんだよ意味わからんのだけど(笑)
言いたい事が山ほど……
ページや時間がふんだんにあれば、それぞれを高い次元で両立することはできるでしょうけど、いわゆる「持ち込み」でも、ページ数が多いほど読む編集者の負担増になってしまいます。漫画賞ではページ数の制限があったりしますし、一部を除いては普通は8ページ単位の構成です。
恐ろしく面白いネームが描ければ別なのでしょうけど、長い作品って逆効果の場合がほとんどなんです。
自分が編集者だったとして、他の作業してる時に時間空けさせられて別の原稿読まされるわけですから、それは完結に描かれているほうがいいでしょうね…。
あと、読み手の思考・・・自分が思うに、文系か理系かで、とらえ方が全く違ってくるのではないかと。
最近から漫画を色々読むようにしてますが、雰囲気重視の漫画とか絵が可愛いだけの漫画はあまりそそられず…一方で何らかの知識を得られる作品は図柄に関係なしに好きだったり、設定の狂いとかに目がいきがちな性格です。これは自分自身が理系タイプだからだろうなと。
読み物でも圧倒的に解説書とかが多いですし、文章を書くのも解説を作るのは何の苦でもありません(この記事も解説の一種かも)
感情表現を追求するよりも、仕組み作りが得意な脳みそでできていると自負しています。
そんなわけで新刊が完成し、これを出版社等への営業へ活用しようと考えているわけですが、果たして「仕組み作り」を得意とするオッサンの書いた漫画がどのくらい受け入れられるのか…編集者ってたぶん文系出身の方が多いと思うんですよね。水と油という感じです。
水分であるお酢と油、そこに卵があればマヨネーズの完成なんですが、その卵たる漫画原稿の確保が非常に難しいって感じでしょうか。
業界人の事をクリエイターと言います。
その業界の中で生きていくために流れをとらえ、それを取り入れていくことは必要な事なんだろうなと。
経験談なのだから間違いない事だと思います。
一方、業界にいる事。流れに乗ればクリエイティブと言えるのか?という疑問もあります。
何かを生み出す人のことじゃないのかと。
そんな事考えるから最前線に上がれない、ということになるのですが。
今考えれば、もっと早くから漫画に取り組んでおけばよかったと後悔してます。
中高生の時には一応は描いてたんですよ。見せられるレベルじゃないですけど(笑)
その時続けて今のように取り組んでいれば、たぶん「青田買い」されていたかもしれません。
しかし、もしそうしていたらネタで悩んでいたことでしょう。
その時は釣りにサバゲーに、仕事に明け暮れていた日々があったわけで、今描いている漫画はその時の経験のアウトプットなわけですから。
後悔はしてるけど、後悔してませんみたいな(笑)
ラジオのテレフォン人生相談で、加藤諦三先生が「変えられる事は変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう」とおっしゃっています。
後悔してても変えられないことは変えられないんで、変えられる事をどんどんやっていくしかありません。
そこに自分の「仕組み作り」が役立つわけです。変える事、ですね。
流れに乗るのが一番楽ですが、新たな流れを作る…仕組みを作り変えてしまえばいいじゃない。
決して簡単な事じゃないのだけれど、これこそかなりのクリエイティブじゃないですかね。
「漫画に機能を持たせる」
これが自分が当面目指すべき仕組み作りなんだろうなと。
そういや、釣り方を開拓したり、オモチャって言われてた機材で精度の高い刺繍作る手法編み出したり
その手の事色々やってきたわけですし。
たぶん手法を追求してどっかで諦めなければできるなと。
というわけで、ちょっとした閉塞感の中ちょっとガス抜きさせていただきました。
Posted by モソの中の人 at 08:25



 県内書店・釣具店で好評発売中!!
電子書籍(Kindle版)はお手軽価格で配信!!
県内書店・釣具店で好評発売中!!
電子書籍(Kindle版)はお手軽価格で配信!!
 ①沖縄ライトゲーム初級編
①沖縄ライトゲーム初級編
 ②沖縄都市河川渓流/
ジャングルパーチ編
県内書店・釣具店で
好評発売中!!
②沖縄都市河川渓流/
ジャングルパーチ編
県内書店・釣具店で
好評発売中!!