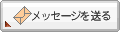2013年08月20日
シリーズ-魚の沖縄方言名-カマジーガーラとトカキン
興味がほかに移る前に書いておこう。
時々、ふと「沖縄の魚の方言名」について考える。
最近、海外で男性の股間を食いちぎる「パクー」という魚を見て、これは恐怖のタンメータニクーヤーだな・・・などと思ったりしたんだけど、その後また沖縄の魚をちょくちょく考えていた。
特にガーラが知りたいんだけど、発音は「河原」「瓦」と同じ。
瓦のような形だからガーラ?淡水に強く河原にも現れるからガーラ?
「ガー」と「ラ(ラー)」に分解すると「ガー(皮)」「ラerまたはルer」になり、ギラギラの皮が何か関係しているのではないか・・・などなど興味は尽きないけど、まだまだ解決できそうにない・・・方言でラまたはルってどんな意味なんだろう?
ガーラに関しては、釣り業界でも10年くらい前まで厳密に分類して扱われることがなかった。
ガーラはガーラ。カスミアジもギンガメアジもオニヒラアジもガーラ。
魚類額専攻していた人が、ヒラアジ類は分類が難しいという話をしていたんだけど。習性(及び釣り方、攻め方)が明らかに違うので、最近はロウニンとかオニヒラとか呼ばれるようになった。
中には「カマジーガーラ」など特別に名前が付いたロウニンアジもいて、ロウニンアジを狙う人はカマジー(鎌尾?)ガーラと区別していたんだけど、かつては一般的にガーラはガーラだった。なぜ、ロウニンアジのみカマジーだったのか?
もちろん、巨大で強い魚だったというのもあるかもしれないけど、ここからは自分なりの考え方を書いてみる。
沖縄はかつて琉球王国だった。
琉球王国に関しては、海に囲まれた豊かな王国だったというイメージがあるんだけど、おそらくそんな事はなかった。
というのも、台風があり、干ばつがあり、強い季節風(ミーニシ・ニングヮチカジマーイ・カーチベー)があり、クチャや国頭暦層を母岩とした土壌は保水性が少ない。
作物は台風や干ばつにやられ、海は荒れていること(海がどの方向に向いているかでシーズンにより変わる)が多く、リーフに囲まれている分、静かな海で漁ができる反面、座礁等の危険もあった。そのうえ決して軽くない税も化せられていた。このあたりはもっと調べてみたいんだけど、宮古島の人頭税石の話があったり、民謡の「クンジャンサバクイ」も納税(年貢)を収めるための労働歌だったとラジオで聴いた記憶がある。
高温多湿な気候では、食べ物をすぐに腐らせる。
夏に取れる「冬瓜」は皮が固く、冬まで持つから冬瓜だという(昨日食べた)けど、基本的に本土のような保存食作りに適さない。
採っては消費の繰り返しだったのではないかと思う。
(ダムや電気のある生活に感謝・・・)
あともう一つ考慮しないといけないのは、各村(集落)はそれぞれ隔離されていたという話もある。
村と村の行き来が制限されていて罰則もあったとか。その罰則が重税であったそうで、よく言えば村人同士で助け合う「ゆいまーる精神」。
逆の見方をすれば、村人同士の監視社会であったという。
沖縄の政治や報道、言論の場でも、「異論は許さない」という風潮から見ても、また、以前調べた民謡「谷茶前」のなりたちを調べても、上記の考察は的を得ていると思っている。
こういう基本ベースを考えて、ウチナー芝居などに出てくる「毛遊び(もーあしび:毛・・・つまり原っぱで行う合コンみたいなもの。実際はもっと過激だったか?)」なども理解できるし、民話などもなんとなくバックグラウンドが見えてくる。
そこまで書いたうえで、カマジーガーラ(ロウニンアジ)とトカキン(イソマグロ)の話に移ってみよう。
魚は沖縄のソウルフードであるブタや、お祝いの席などで振舞われるヒージャー(ヤギ)などと同じく、貴重なタンパク元だった。
しかし、いつでも漁にいけるわけでもなく、常に獲物があるとは限らない。おまけに高温多湿の環境において、すぐ腐る。
小さな魚では家族が食えるかもしれないし、通貨または何らかの経済活動に変えられるかもしれないし、量によっては家族が食えないかもしれない。
少し大きな魚が取れれば、親戚まで当たるかもしれない。アカジン(赤銭・・・換金性が高い)であれば、換金してしまうかもしれない。
ロウニンアジだったらどうだろう?
高温多湿ですぐ腐ってしまい、また、味は特別美味しいというものでもなく、換金性が高いわけでもない。
運ぶのも大変だ。
干ばつや台風、村々との往来が規制されている中、村に振舞われたとしたら、これほどのご馳走はないと思う。
なので、他のヒラアジ類と比べると「特別な存在」だったのかもしれない。
それで、カマジーガーラと、他の魚とは別に分けられていたのではないかと・・・
そしてもう一つ「トカキン」について。
トカキンはイソマグロのことで、またの名を「イノーシビ」という。
シビはマグロのことで、チンバニーシビ(金羽シビ:金ヒレマグロか?。キハダマグロ)やウシシビ(クロマグロ・本マグロ。ウシのようなマグロ)などの名前がある。
マグロの古語でありかつては江戸でも「シビ」と使われてたそうだ。
(死日=縁起が悪いとマグロになったという、さかなくんの話があった)
そんななか、トカキンはなぜトカキンだったのか?
同じ響きの魚の名前を探しつつ、「トカ」「キン」に分解する。
すると、「トカ(トゥカ)」と付く魚に「トカジャー」と呼ばれるニザダイ類が出てくる。
「10日間カジャー(臭い)が取れない、癖のある臭いの魚」という意味で伝えられてるが、トカキンも「10日(10日間)キン」じゃないと予測できる。
ではキンは何なのか?金武はたぶんチンと発音する・・・あれ、クロダイ類のチン?
そこで「キン」「キィン」などで考えてみると、「消える」とかそういう意味になるではないかと考えた。
トカキンはマグロ類のくせに、あまり美味しくない魚であり、足が速い(腐りやすい)魚だと思う。
10日間かけないと消えない、手をつけたがらない魚だったのか?
それとも10日間で腐って消えてしまうという意味だったのか?
方言の学者さんとかが入って調べると面白いかもしれない。
以上、思いついたことをダラダラ書いてみました。
Posted by モソの中の人 at 09:25
│海歩っちゃー



 県内書店・釣具店で好評発売中!!
電子書籍(Kindle版)はお手軽価格で配信!!
県内書店・釣具店で好評発売中!!
電子書籍(Kindle版)はお手軽価格で配信!!




 ①沖縄ライトゲーム初級編
①沖縄ライトゲーム初級編
 ②沖縄都市河川渓流/
ジャングルパーチ編
県内書店・釣具店で
好評発売中!!
②沖縄都市河川渓流/
ジャングルパーチ編
県内書店・釣具店で
好評発売中!!